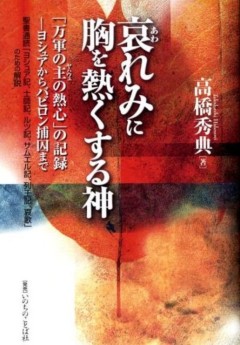
「主があなたがたを恋したって……聖書の基礎(モーセ五書)の解説」に続く聖書通読のための解説。歴史的な文脈、核心となる原文の解説、新約聖書との関連、現代への適用を含んで「ヨシュア記から列王記、哀歌」までを1冊に。詩篇の解説「心を生かす祈り」とも併せて読めば、旧約世界が、より清冽に現代に語りかけてくる。
発売日:2008年10月20日
発行:いのちのことば社
ISBN:978-4-264-02714-0
定価:2,286円(税別)
「はじめに」
「旧約聖書は、どうもとっつきにくくて……」という方も多いかと思われますが、この本はそのような方々を意識して記させていただきました。確かに時代も場所も、あまりにも私たちの生活の場から遠く離れているように思われますが、ここで扱っているヨシュア記から列王記の物語ほど、その原則を現実の生活に適用できる教えはありません。そこに記されている三千年前の人間の現実は私たちに驚くほど身近なものだからです。たとえば、私たちは、ギデオン、サムソン、サウル、ダビデなどの物語と、自分の人生を重ね合わせて見ることができます。
旧約と新約の違いについて、しばしば、「旧約は目に見えるカナンの地に神の国を建てることが、新約においては、天の御国を受け継ぐことがテーマとされている」と言われます。私はそのような説明を聞き、霧が晴れたような気になったことがあります。旧約で残酷な話が出ざるを得ないのは、目に見える土地の所有権が問題になっているからです。この地上の富に目が向かえば向かうほど、人と人との利害が対立せざるを得ません。しかし、私たちの心の目が、来たるべき世界に向かえば向かうほど、人と人との平和が実現しやすくなるのではないでしょうか。
ところが、そこに落とし穴があるかもしれません。信仰者は、すべての希望を天国に置くべきで、この世の事に関しては禁欲的な態度を取るのが聖書の教えであるかのように誤解することがあり得るからです。少なくとも私にとって、国際金融の世界で働いているとき、「天国への希望」よりは、「今ここで、生きて働いておられる神」に関しての教えのほうがずっと身近に感じられました。私たちは誰も、この世に生きている限り、目に見える富や力から自由になることはできません。日々、自分の仕事や家族の将来のことで悩み、そのことのゆえに神を求めているのではないでしょうか。信仰とは、私たちの心をこの世の現実から逃避させるものではなく、この矛盾に満ちた世の中において、「生きる」力を与えることができるものであるはずです。
なお、新約の福音を、「肉体が滅んでも、たましいが天国に行ける」というような枠で理解しようとする方は、聖書を誤解しているのかもしれません。たとえば、福音書に最も頻繁に繰り返されているテーマは、「神の国」または「天の御国」ですが、このことばの意味を、ダビデ王国の成立と滅亡という歴史的事実から離れて理解することは不可能です。残念ながら、旧約聖書を知らずには、新約聖書におけるイエスのメッセージは本当には理解できないと言えましょう。
この本のタイトルは、この世界の創造主であられる主(ヤハウェ)が、ご自身の民として選ばれたイスラエルをさばく際に、「わたしはあわれみで胸が熱くなっている」(ホセア一一・八)とご自身のお気持ちを表現しておられるみことばを基にしています。「哀れみ」と漢字で書いたのは、そこに何よりも、神の深い「哀しみ」の気持ちが込められていることを表現するためです。またこれは、原語は違いますが、最後の解説「哀歌」に結びつきます。
聖書の最初の五つの書の結論でモーセは、「私は、いのちと死、祝福とのろいを、あなたの前に置く。あなたはいのちを選びなさい」(申命三〇・一九)と勧めました。ところが、イスラエルの民は「のろい」を選んでしまいました。主は、彼らの不従順に忍耐を重ねながら、ダビデのもとでアブラハムに約束したカナンの地すべてを占領させ、ご自身の臨在のしるしとしてのエルサレム神殿をソロモンのもとで完成させてくださいました。しかし、彼らはその後も、反抗に反抗を重ねます。その結果、北王国イスラエルはアッシリヤによって滅ぼされ、南王国ユダはバビロンによって滅ぼされました。拙著、『主(ヤハウェ)があなたがたを恋い慕って……-聖書の基礎(モーセ五書)の解説-』で、申命記の結論は、ルカの福音書一五章の放蕩息子のたとえに通じると記させていただきました。そこで放蕩息子の帰還の時の様子が、「まだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き、口づけした」と描かれます(二一節)。同じように、主(ヤハウェ)は、自業自得で「のろい」を選び取ったイスラエルの苦しみをご覧になりながら、「哀れみに胸を熱く」しておられるのです。
なお、「胸が熱くなる」という表現は、I列王記三章で、知恵に満ちたソロモンが、ひとりの子を奪い合うふたりの母のどちらが実の母親かを見分けるため、わざとその子を半分に切り裂いて分けるようにと命じたところ、実の母が、「自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、『どうか、その生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください』と王に申し立てた」(二六節)という箇所にも見られます。この母のことばで、どちらが実の母であるかをソロモンは見分けることができました。
哀れみに胸を熱くする「母」ということで、聞き続けてきた話があります。私は一九五三年三月に北海道の大雪山のふもとで生まれました。大変な難産で、自宅で私を産んだ母は、大量の出血を助産師さんに雪で止血してもらいながら、死にかけたとのことです。どうにか命を取り留めた母は、休む間もなく農作業に出ました。ひとり家に置かれた幼児の私は、泣くばかりでした。あるとき、声がしないと思ったら、おくるみで鼻と口が塞がり、窒息しかけていました。
それで、一歳を過ぎた後の田植えの時期には、父が持ち運びできる小さな屋台を作ってその中に寝せ、あぜ道に置きながら父母は農作業をしていました。ところが、私は風邪をひいて四十度以上の高熱が続き、喉の奥全体を腫らし、ついには呼吸困難に陥りました。どうにか、三十キロメートルあまりも離れた旭川の市立病院にバスを乗り継いで運ばれました。幸いその分野では北海道一と言われる院長先生に診てもらえましたが、「あきらめてください」と言われるほどの重症でした。しかし、必死に懇願する母の願いで荒療治が行われました。三人の医者と、何人かの看護師の方のもとで、一歳の私は逆さにされ、喉が何度にも分けて切開されました。そのたびに大量の血が流れ、脈がストップしたとのことです。しかし、そのたびに母が抱くと、心臓が再び鼓動を始めました。それが何度も繰り返され、命を取り留めたとのことです。その後も、何度も、死ぬ寸前の危険に会いました。そのため発育が極端に遅れ、小学校に入った頃は、三月生まれだったことも相まって、運動も勉強でも「落ちこぼれ」という状態でした。
幼児期の苦しみは、心にもマイナスの陰を落とします。また、発育の遅れは、強い劣等感の原因になりました。私の記憶にかすかに残っているのは、ひとり泣きじゃくる自分の姿です。その後も、何をやっても遅れを取る落ちこぼれ意識を培ってきました。どうにか小学校高学年からめきめきと成績が良くなりましたが、幼児期の心の傷は、私の心に暗い影を落とし続けていました。念願の大学に入り、国費の交換留学で、米国で学ぶことができ、不思議な導きでイエス・キリストを主と告白する信仰に導かれました。そのときの私は、自分の内側にある真の問題には気づいていませんでした。ただ、その後の信仰生活の中で、徐々に自分の心の奥底に隠されている何ともいえない不安と向き合いながら、自分はこの不安のゆえにイエスのもとに引き寄せられたのだと分かりました。しかし、そこで「信仰によって不安を克服しよう!」などと思っても、どうにも変わりようのない自分の不信仰に悩むという空回りが起きて来ました。
しかし、自分の人生を「神の選び」の観点から、優しく見直すことができるに連れ、気が楽になってきました。先の市立病院の先生にはその後も助けられましたが、「ほんとうによく助かったね……」と感心されたそうです。私たちは誰しも、生かされて、生きています。その過程で命の危険に何度も遭遇します。私を生かすためには、心臓が止まるほどの乱暴な治療が必要でした。しかし、「哀れみに胸を熱くする母」の愛が、私の心臓を動かしました。そして。今、そのときの母の背後に、「哀れみに胸を熱くする神」がいてくださったことが分かります。私は、神の燃えるような愛によって、目的をもって生かされています。そこでは、私にとってマイナスとしか思えなかった体験も、益として用いられるということが分かってきました。
私たちは多くの場合、幼児期に何らかの心の傷を負います。そこから自分を被害者に仕立てる人生の物語を描くことは簡単です。しかし、私たちは、人生の物語をまったく別の観点から、信仰を持つこともできない幼児期から描き直すことができます。それはひとりひとりに創造主が期持しておられる人生の物語です(詩篇一三九・一七、一八、拙著『心を生かす祈り』参照)。ただしそれは、私たちの主体性が失われ、決められた一本のレールの上を走るということではありません。
たとえば、ソロモンの記事に出てくる母は、子どもを生かすために一度は子どもを手放す決意をしましたが、両親も「私を生かす」ことを第一に考え、先祖が命をかけて北海道に開拓した水田を受け継がせなければならないとは考えませんでした。同じように、神は、私たちの主体性を重んじながら、ご自身を隠すようにして、私たちの人生を導いておられます。ただそのため、神を身近に感じることができず、自業自得の苦しみに会うこともあります。しかし、それは私たちを束縛しようとはされない神の愛の表れなのです。
そしてしばしば、神の選びは、苦しみを通して初めて見えてくるという面があります。それは、自分の出生の環境自体を「神の選び」の観点から見直すことから始まります。そのことを使徒パウロは、「神は私たちを世界の基の置かれる前から彼(キリスト)にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされました。神は、みむねとみこころのままに、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられました」(エペソ一・四、五)と記しています。ここで「私たち」に含まれるのは、「イエスは主です」(Iコリント一二・三)と告白しているすべての人々です。あなたがイエスの御名によって、イエスの父なる神に祈っているのは、あなたのうちに創造主の御霊が生きて働いておられることの結果です。あなたは神に選ばれた「高価で尊い」存在なのです(イザヤ四三・四)。
同じようにイスラエルに対する「神の選び」は、イスラエルの苦しみの歴史を通して明らかにされます。しばしば、旧約の物語を読む方が、神の残酷さに失望と驚きを感じます。しかし、それは話の一部しか見ていないために起こる誤解です。神は「十のことば」において、「わたしは主(ヤハウェ)、あなたの神、ねたむ神である。わたしを憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、わたしを愛し、わたしの命令を守る者には、恵みを千代にまで及ぼすからである」(出エジプト二〇・五、六、前半は私訳)と言われました。そして、偶像礼拝に走ったイスラエルに対する神のさばきは、神の「ねたみ」から生まれていると聖書では描かれ、それは「燃える怒り」にさえ至ります。それは多くの人に納得し難く思えますが、「ねたみ」というヘブル語は「熱心」と訳されることばと基本的に同じです。II列王記一九・三一では、神がユダの家を、苦しみを通して整え、豊かな実を結ぶようにされることを指して、「万軍の主(ヤハウェ)の熱心がこれをする」と描かれますが、これはイスラエルを苦しめながら最終的に救い出す神の燃えるような愛の表現です。この「熱心」ということばは、雅歌では「ねたみ」と訳され、「愛は死のように強く、ねたみはよみのように激しい」(八・六)と描かれます。イスラエルをさばく神の「ねたみ」は、燃えるような神の愛の表れなのです。この書の副題を、『「万軍の主(ヤハウェ)の熱心」の記録-ヨシュアからバビロン捕囚まで-』としたのはそのためです。
ところで、サムエル記第一では、神がサウルを王として立てられたことを「悔いた」という不思議な表現があります(一五章)。これが聖書に最初に出てくるのは、ノアの箱舟のところで「主(ヤハウェ)は、地上に人を造ったことを悔やみ、心を痛められた」(創世六・六)という表現です。どちらも、神のさばきの原因となることばです。しかし、このことばと、先の神の「哀れみ」とはヘブル語で同じ語根のことばなのです。またこのことばは「慰める」とも訳されます。「さばき」と「救い」をもたらす神の「思い」が同じことばで表現されるのは、何とも不思議ですが、それこそが十字架の神秘です。イエスの十字架は、罪に対する神の「さばき」であるとともに、罪人に対する神の「哀れみ」だからです。そして、その底には、神の「哀しみ」があります。私たちは聖書を読むときに、この神の感情を忘れると読み間違いをしてしまいます。どちらにしても、多くの人々が、首を傾げる表現、神の「ねたみ」とか、「悔やみ」ということばは、実は、「神の燃えるような愛」と表裏一体のことばなのです。
ところで、私たちは仕事でドイツに駐在中に、日本人のための家庭集会を開いていましたが、そこに会社の同僚が来てくれました。その日のテーマはたまたま、ダビデとサウルの対比でした。彼は、「サウルとダビデの罪を比べると、まだサウルの罪の方が軽いように思う。なぜ神はサウルをしりぞけ、ダビデにこれほど寛大なのか分からない……」と言っていました。残念ながら、当時の私はその疑問に十分に答えることはできませんでした。今回、この解説を記しながら、そのときのことが思い起こされます。私は、神が私たちに対して抱く「情熱として愛」を理解していませんでした。そして、今も、多くの人々が、それを理解していないように思われます。このいのちにあふれる主(ヤハウェ)と人間との愛のダイナミックな愛の物語を、単なるいのちのない道徳の教えに変えてしまい、そこにある神の情熱を読み取ることができなくなっています。
ヨーロッパの歴史で、誰よりも大胆にキリスト教を否定したニーチェは、ドイツのルター派国教会の牧師の息子として生まれましたが、五歳のときに父が亡くなり、母と妹とともに親戚の世話を受け、肩身の狭い思いをして育ちます。彼の母も牧師の家に生まれていましたから、母は彼が牧師になることを望んでいました。しかし、彼はヨーロッパを代表する無神論者になってしまいました。彼は晩年の書『アンチクリスト』で、「高級な人間と呼ばれる牧師」こそ、実は、「いのちを否定し、誹謗し、損なわせることを職業としている者である」と言っています(Friedrich Nietzsche Der Antichrist 8私訳)。自分の親たちの働きを、「いのち」を抑圧するものと描かざるを得ない現実を彼は感じていたのです。何と悲しいことでしょう!
一方、ニーチェは同じ書で、「イスラエル王国の時代……ヤハウェは、力の意識の表現であり、それは喜びと希望の表現であった。人々はヤハウェに勝利と救いを期待していた。それは特にヤハウェが自然を支配し、民に必要な雨を降らせることを意味した……ところが、人々は神の概念を不自然なものに変えた……いのちの表現ではなく、道徳に……人間の想像力(ファンタジー)を根本的に悪化させるものに……」(同25私訳)と、後代の人々が「いのち」の教えを、いのちのない道徳に作り変えたと非難しています。しかも、彼は、「道徳の系譜」で「旧約聖書にあらゆる敬意を払え!そこに私は……地上に類稀な、強い心の比類なき純真さ(原語「ナイーブ」)を発見する」(Zur Genealogie der III Moral 22)とさえ語っています。彼は旧約聖書が大好きだったのです。しかし、残念なことに、新約聖書を、天国への希望を語りながら人間の自然な感情を抑圧する禁欲主義の教えと誤解してしまいました。そして彼は、何よりも教会の権威が嫌いでした。そんな彼は、道徳としての「愛」ではなく、「情熱としての愛」(die Liebe als Passion Jenseits von Gut und Böse 266私訳)を何よりも高貴なものとして見ています。
そして、ニーチェとほぼ同時代の哲学者ゼーレン・キルケゴールは、当時の教会を批判しながらもイエス・キリストを熱く信じた哲学者ですが、ニーチェに通じることを次のように言っています。「牧師たる者は、もちろん、信仰者でなくてはなるまい。では信仰者とは!信仰者とはもちろん、恋する者である。いやしかし、恋するすべての者のうちで最も熱烈に恋する者でも、信仰者に比べると、その感激の点では、実はほんの青二才でしかない」(キルケゴール「死に至る病」桝田啓三郎訳、中央公論社刊、『世界の名著』40、一九六六年、五四八頁)。
このふたりはともに、道徳としてのキリスト教を批判したことで共通しています。彼らにとっての「愛」とは、道徳ではなく「情熱」だったのです。ところが皮肉にも、現代の人々が旧約聖書を読みながら何よりもつまずきを覚えるのは、現代の道徳観念に反することが記されていると思えるからです。しかし、それは聖書がこの世の道徳を越えているというしるしでもあります。どの宗教にも共通するような「道徳」、それは人間の頭で思い浮かべることができる常識です。しかし、「なすべき良いことがわかっていながら、それができない……」というのが人間の現実ではないでしょうか(ローマ七・一八参照)。聖書には、私たちを背後から突き動かす、神の燃えるような愛が記されています。その愛に動かされている者は、結果的に、この世の道徳が求める以上の愛を実践することができることでしょう。愛は愛によってしか生まれません。そして、福音こそは、私たちの中に、自分の利害を超えて神と人とを愛する力を生み出すことができます。
なお、この書は、私が牧師として奉仕させていただいている立川福音自由教会の礼拝メッセージの原稿として用意したものを加筆、修正したものです。当教会では聖書を全体として理解することを大切にし、「木を見て森を見ず」の信仰にならないように、ひとりひとりが聖書の中に自分の人生の物語を発見できるようになることを目標に、速いペースで聖書を読み進んでいます。
先の『主(ヤハウェ)があなたがたを恋い慕って……-聖書の基礎(モーセ五書)の解説-』に関しましても、これだけの広い範囲を一冊の本にまとめたことが画期的であるとの評価を何人もの専門家の先生からいただいております。残念ながら、聖書を通読するに当たり、ことばの意味から時代背景、新約との関係、現代への適用までも含めた手軽で安価な解説書は日本では見当たらないように思われます。聖書通読の際の参考書としてお用いいただけますなら望外の幸いです。なお、当教会では新改訳聖書第三版を用いており、基本的に引用聖句はそれに基づいております。
当時の歴史と地理をより分かりやすくするためのオリジナルな年表と地図を巻末に三つ折でつけさせていただきました。地図では標高差が分かるようにしたり、年表では王の特徴をひとことで表現するなど、様々な工夫がなされておりますので、この書を読む際にお役に立てていただければ幸いです。
目次
はじめに
ヨシュア記
1章~3章「みことばを味わい、主に頼り、一歩を踏み出す」
4章~6章「主の勝利を思い起こしつつこの地に生きる」
7章~9章「主との交わりを失う悲劇と回復される祝福」
10章、11章「神の戦いの昔と今……小羊の王国」
12章~19章「神から与えられた責任を果たす喜び」
20章~22章「神の平和をこの地に実現するために」
23章、24章「主を愛し続けることの難しさ」
士師記
1章~5章「主を怒らせる民に対する救い」
6章~9章「神の救いを人間の働きとする悲劇」
10章~12章「主に用いられながら、主を知らなかった人」
13章~16章「孤独なナジル人サムソン」
17章~21章「めいめいが自分の目に正しいことを行う中での悲劇」
ルツ記
「のろわれた民の娘から祝福された王家の母へ」
第一サムエル記
1章~3章「悩みから生まれた驚くべき救い」
4章~7章「礼拝の場を壊して礼拝を建て上げる神」
8章~12章「主(ヤハウェ)こそが王である」
13章~15章「神に聞く代わりに、人の顔色を見た王の悲劇」
16章~18章「おびえるサウルと主にまっすぐなダビデ」
19章~21章「信仰と友情」
22章~24章「恐れを祈りに変えたダビデ」
25章、26章「神の怒りに任せなさい」
27章~31章「主によって奮い立つダビデと自滅したサウル」
第二サムエル記
1章~5章5節「神の時が満ちるのを待つ」
5章~7章「ダビデからキリストへ」
7章~10章「神の真実とダビデの真実」
11章~13章19節「ダビデの恐ろしい罪と神の赦し」
13章20節~15章18節「ダビデの沈黙が生んだ悲劇」
15章13節~17章「主が、のろいに代えてしあわせを」
18章~20章「最も身近な人が苦しみの原因となる」
21章~24章「天の王に従う地の王として生きる」
第一列王記
1章~3章「主(ヤハウェ) のしもべとして生きる王」
4章~6章「神の御住まいが建てられるために」
7章、8章「救い主を指し示すソロモンの神殿」
9章~11章「私たちの憧れの中にある罠」
12章~14章「真の王を忘れたイスラエルの悲劇」
15章~17章「生ける神との愛の交わり」
18章、19章「主(ヤハウェ)の前に立たせる沈黙の声」
20章~22章「主(ヤハウェ)の怒りを引き起こす生き方」
第二列王記
1章~3章「わたしの光となりなさい」
4章~6章23節「神の恵みをむだに受けないようにしてください」
6章24節~10章「この世の王国と小羊の王国」
11章~13章「主(ヤハウェ)の名を呼ぶ者は、みな救われる」
14章~16章「神の子としての謙遜と誇りに生きる」
17章~19章「万軍の主(ヤハウェ)の熱心がこれをする」
20章~23章「主の怒りと救い」
23章28節~25章「エルサレムの陥落の意味」
哀歌
1章~3章39節「苦しみが意味するもの」
3章40節~5章「哀歌からクリスマスへ」
あとがき
付録
「古代イスラエルの地図」「古代オリエントの地図」
年表「イスラエルの歴史」
年表「イスラエル王家の歴史」
おわりに

